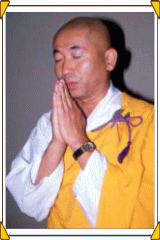| 銃口を向けられても、投獄されても、ただただ平和を訴え地球上の紛争地を歩く僧侶がいる。誰もが注目しない問題でも、マスコミや市民運動が忘れても、寺沢潤世さんだけは、今日も地球のどこかを歩いている。 |  |
平和を願い地球を歩く僧侶
月刊あれこれ03年5月号
| 銃口を向けられても、投獄されても、ただただ平和を訴え地球上の紛争地を歩く僧侶がいる。誰もが注目しない問題でも、マスコミや市民運動が忘れても、寺沢潤世さんだけは、今日も地球のどこかを歩いている。 |  |
この原稿を書いている三月二〇日、アメリカはイラクへの空爆を開始した。
その砲火の下には、日本山妙法寺の僧侶、寺沢潤世さん(五三)がいる。今、どれほどの怒りと悲しみに身を焦がしていることだろう。
今回の空爆前、日本人も含め、多くの国から「人間の楯」希望者がイラク入りした。マスコミもどのチャンネルもイラクを大特集している。日本でもあちこちの街で反対デモが起こっている。ハンガーストライキをやる人もいる。インターネットでは「戦争反対」の文字が踊っている。日本のどこからも熱気が漂ってくるようだ。
とはいえ、この熱気もあと数ヶ月もすれば冷める。ほんの一年半前でも、アフガニスタン空爆への熱い関心があっという間に薄れてしまったように。
しかし、一人寺沢さんに関しては、平和への希求の思いを灯し続けている。一二年前の湾岸戦争。イラクとサウジアラビアの国境に設置された「人間の楯」キャンプには十六カ国から七二人が参加したが、寺沢さんはたった一人の日本人だった。寺沢さんは、その前からも、そして、その後今に至るまで一日たりとも休むことなく、紛争地で平和を祈り、三五年間歩き続けている。そこにあるのは「熱気」ではなく一途な「信念」だ。
予定に従えば、三月一一日から一七日までの一週間、寺沢さんはイラク国内一四〇キロの平和行進を行ったはずである。いつものように黄色い袈裟を着て、ウチワ太鼓を鳴らし、南妙法蓮華経を唱えながら。
非暴力の世界へ
一九六九年一二月。七〇年安保闘争が盛り上がっていたときのこと。立教大学に入学したばかりの寺沢さんは、新宿で、機動隊と学生とが、催涙弾と火炎ビン、ジュラルミンの楯とゲバ棒とでぶつかり、流血の修羅場と化すのを目の当たりにした。
「どちらが勝ったにしても、これでは本当の平和は来ない!」
そう思ったら決めていた。絶対非暴力を貫く日本山妙法寺の僧侶になろうと。七〇年四月、寺沢さんは退学届を出し出家得度した。一九歳だった。
寺沢さんは高校生のときに家出をしたのだが、そのとき、叔父の紹介で日本山妙法寺に数ヶ月間身を寄せていて、その非暴力の思想に既に感銘を受けていたのだ。
日本山妙法寺。故・藤井日達氏(一九八五年没)が一九一八年に、日蓮の教義を伝えるべく創設。絶対非暴力・非武装の国家建設を目指す、まず行動ありきの仏教団体である。世襲ではなく誰でも入門でき、檀家をもたず、墓地経営をしない。過去にも、砂川闘争、三里塚闘争の現場で非暴力闘争運動を貫徹し、靖国法案反対運動にもデモの先頭に立った。今回のイラク空爆でも、いろいろな宗教者を集めてアメリカ大使館前での行動を起こす「平和を祈念する宗教者のつどい」の事務局にもなっている。
約二百人いる僧侶のうち、約五十人が海外で開教活動や仏舎利塔建立に携わっている。そして、寺沢さんも、出家の半年後には、仏舎利塔建設のためにインドに派遣された。
平和行進との出会い
寺沢さんが紛争地帯を歩き始めたのは、日本山妙法寺の道場のあるボンベイ市だ。今もそうだが、絶えずヒンズー教徒、イスラム教徒、仏教徒とが対立し、流血事件を起こしていたボンベイ。
寺沢さんは、暴力に対抗するには非暴力の行動しかないと主張し、周囲の反対を振り切り、南無妙法蓮華経を唱え、ウチワ太鼓を鳴らしながら騒乱地区を歩きだしたのだ。案の定、石が飛んできた。
だがまったく怖れはなかったという。
「その行動こそが師の教えであり、仏の教えであるからです。やっと仏弟子らしい生活ができると充実感で一杯でした」
そして、これを何度も繰り返すと、宗教に関係なく人が数キロにもわたって通りに溢れ、そこだけ争いがなくなり、地面に頭をすりつける人も現れた。
そして、寺沢さんのその行動は、ヨーロッパでより地球的へと変貌する。
七五年七月。イギリスでの開教のため、寺沢さんは一人インドからロンドンに向かう。そこで出会ったのが、当時、良心的兵役拒否者が中心となり、数千人、数万人規模の市民が一緒になって歩く平和行進運動である。寺沢さんは、多くの市民とジュネーブの国連まで歩いたり、高速増殖炉スーパーフェニックスに反対する平和行進に参加することで、平和を願う人々との連帯が深まっていくのを実感していた。
歩く人すべてが主人公たりえる平和行進。
「これだ。この若者たちとの出会いこそ仏様のお計らいだと本当に感謝しました」
その後、寺沢さん自身が企画しての平和行進も幾度か行われるが、その「本気」を如実に顕したのが、東欧を歩いてのベルリンの壁への平和行進である。
八三年三月、寺沢さんは、東西冷戦の象徴であるベルリンの壁へ向かって、平和を訴えながら、西からと東からの日本山妙法寺の二隊が歩き、壁を挟んで合流するという計画をたてた。だが、計画は頓挫寸前に追い込まれる。東奥側の平和委員会が、何ヶ月も交渉を重ねても、許可を出さなかったからだ。
思いつめた。だが諦める気もまったくなかった。そして、寺沢さんは仏教として残された最後の手段に出る。仏に祈るのだ。ただし、決死の覚悟で。
イギリスのミルキントーンズ市に、八〇年、寺沢さんが中心になって建立した仏舎利塔がある。ある夜、そこで、寺沢さんは、香油を染み込ませた綿を左手の人差し指に巻き火をつけた。松明と化した指に祈りを投げる。「ベルリンの壁まで歩かせたまえ」と。
骨が半分露出した指に包帯を巻いたまま、三月、寺沢さんは一人ポーランドに飛び、平和委員会を無視して西へ西へとウチワ太鼓を撃ちながら歩き始めた。覚悟をしていた連行や逮捕はなく、それどころか、どこに行っても、各地の教会や一般民家の人々は、異教徒の寺沢さんを歓迎し、宿と食事を提供してくれた。
「完全な無銭旅行でした。あの温かな心を私は忘れません」
東ベルリンも歩き通し、五月、とうとうベルリンの壁に到達する。同じ日、壁の向こう側にも日本山妙法寺の僧侶たちがいた。実に晴れ晴れとした気持ちだったと寺沢さんは振り返る。そしてその後、骨が露出した指はためらうことなく切り落とし、建設中のロンドンの仏舎利塔の礎に埋めた。
思案
八五年一月、藤井日達氏が他界する。その直後から、寺沢さんは、一六歳のときのように、再び人生を考え始めていた。自分に生きる導を示してくれた日本山妙法寺の活動。その活動の柱の一つが、仏舎利塔を建立して仏跡を復興するというものだが、「それ以上に大切なものがあると思ったのです」。
この頃の心境を、寺沢さんはその著書「天に轟け地に潤せ」(地湧社)でこう書いている。
「仏弟子にとっては、法を継ぐということがいちばん大切な仕事です。お師匠様のご遷化のあと、お師匠様がたもたれた法が、この世に留まっていくということは、弟子や信者という教団が続いていくことではない。財産が残っていくことでもない。それは純粋に精神的な問題です。(中略)私の考えはロンドンの仏舎利塔を建てて盛大な落慶法要を迎えるということに向けられるよりも、そういう問題が重く心に突き刺さっていました」
藤井師匠が掘建て小屋に住みながら、仏法を世に広めようとした活動初期の困難な道を自分は歩いているのだろうか? 寺沢さんがこう思うように至るには、逝去前に藤井師匠が残した次の言葉が心に残っていたからだ。
「きれいな仏殿、楼閣のなかにわが病身を養う、この私の晩年の姿を見習えば、もはや日本山の命脈はない」(同書より)
私は日本山妙法寺で活動する僧侶に何回かお会いしたことがあるが、誰もが平和を心の底から願う人々である。だが、寺沢さんは、組織というものに身を寄せての修行そのものに違和感を覚え始めたのかもしれない。寺沢さんは徐々に日本山妙法寺の組織行動から距離をとるようになる。三五歳のときである。
困難との出会い
自分はどう生きるのか。答は出ない。寺沢さんは、初心に戻ろうと一年以上のインド放浪や、母とのインド旅行、仏舎利を携えての数ヶ月間の世界巡礼など、一僧侶としての行動を繰り返した。
転機がやってきたのは九一年。湾岸戦争勃発前に、それを食い止めようと、前述の通り、湾岸戦争での「人間の楯」キャンプに寺沢さんは参加した。そして終戦後、日本のPANというNGOとイラクを何度も訪れ救援活動に携わることになる。
私事で恐縮だが、この頃、私は知人の経営する旅行代理店を臨時的に手伝っていたのだが、偶然にも、PANからイラク行き格安航空券を探しているとの電話を受けた。そこで薦めたのが、ソ連のアエロフロート航空である。当然、モスクワ乗換えだ。ときには数日間滞在することにもなる。
そして、何回も日本とイラクを往復するうちに、垣間見るモスクワに「ソ連はたいへんなところに行く」と寺沢さんは感じていた。
特に、九一年八月、KGB創設者の銅像が倒されるのを目の当たりにし、ゴルバチョフがクリミアで失脚するのを知るにつけ、寺沢さんは、今後の全世界的な平和運動の鍵はソ連にあると確信してソ連での長期滞在を決める。そして年末、ソ連は消滅した。
さて、他の地域でもそうしていたように、寺沢さんはモスクワでも托鉢で過ごしていた。市場に行くと、持ちきれないほどの野菜や穀物をもらっていたのだが、いつも、礼儀正しく積極的にお布施をしてくれる人たちのことが気になっていた。
「それがイスラム教徒のチェチェン人でした。人間に対する接し方が、他のどの集団とも違うんです。例えば、若者は年長者が来たら必ず席を立ち、年長者が座るまで着席しません。その一人で、ルースランという青年と仲良くなったのですが、彼が九三年に急逝します。ご遺体に付き添うことで私は初めてチェチェン共和国を訪れました」
飛行機でチェチェンの地に降り立った寺沢さんは驚いた。ルースランの棺を待つために、ボタン雪が降る中、三〇〇人以上の人々や車が長い行列を作っていたのだ。葬儀も村中の人々が集まり、聞いたこともない節回しで男たちが厳かで深い祈りを捧げていた。祈りが進むにつれ、徐々に死者への気持ちが盛り上がり熱気の波動が伝わってくる。男たちが輪になって大地を踏む音が響いてくる。ルースランは懇ろに弔われ土に還った。
「その魂の深みにただ感動を覚えました」
そして寺沢さんは、ルースランの父から、新たな息子として扱われることになり、以後何度もチェチェンに通うことになるのだ。
そして、九四年十二月。ロシアは突然チェチェンに軍事侵攻を開始する。チェチェンは、ソ連崩壊の九一年に独立宣言していたのだが、それを認めないロシアからの報復だった。
寺沢さんは即座に、零下二十度のなか、赤の広場、国会議事堂前などでウチワ太鼓を撃って和平を訴えた。しかし、厳寒の上にインフレで生活が大変な時、この行動に関心を示す人々は少なかった。
やりぬきましょう!
そんな時、寺沢さんは「ロシア兵士母親の会」の婦人たちと出会う。会は、その九割がもう帰ってこないという、今回の戦争に突然徴兵された息子を戦場から取り戻す運動をしていた。殺されるチェチェン人も、殺す側のロシア兵もどちらも犠牲者ではないか。寺沢さんは提案した――「息子さんたちを個別に連れ帰るのではなく、皆でグルズヌイまでの平和行進をしましょう」
モスクワから三千キロ先のチェチェン国境までをバスで移動し、戦場のチェチェンを平和行進するという計画は異論なく受け入れられ、三月八日、モスクワからバスが出発した。参加したのは三六人。
だが、行く先々で正面切って戦争非難したため、チェチェンの隣国イングーシの首都ナザランで、平和行進団に対し、ロシア軍総司令官はチェチェン入域禁止令を通達するのである。母親たちに同様が広がる。しかし、寺沢さんは励ました――「誰にもできることをやっても人の心は動かせない。やりぬきましょう!」
これは寺沢さん自身の信念でもある。
そして、入域禁止令に抗するように、記者会見で「何があっても歩く。我々が入ったら戦争を中止せよ」と表明し、寺沢さんは既に千人以上に膨れ上がった参加者と歩き始めるのである。
ついにチェチェンに入った。そして、一つ目の村セルノボルスク、二つ目の村サマシキで寺沢さんたちは見た。何キロにも渡り人々が集まっていたのを。「やっと戦争を終わらせる人たちが来てくれた!」「ありがとう! ありがとう!」と涙を流しながら駆け寄ってくるのを。
「凄かった。町中の人が行進に参加して砂塵が巻きあがるほどでした」
そして、寺沢さんたちを感激させたのが、戦争で窮している人々が、寺沢さんたちに貧しい蓄えのなかから最上のものをご馳走してくれることである。なかには、脱走ロシア兵をかくまう人もいるという、その気高い精神に寺沢さんは心を揺さぶられるのを禁じえなかった。
寺沢さんは世界中を歩いているが、特にチェチェンに力を傾けている理由がここにある。
「冷戦終了後、世界は民族対立の時代に入りました。私はそれを乗り越えられる文化的素地がチェチェンにあると信じているんです。異教徒も敵も受け入れる。それが、チェチェンに関わる第一理由なんです」
だが、次の村の手前で、戦車が道を塞いでいた。そして、黒覆面の特別部隊の兵士たちが、一メートル間隔で寺沢さんとロシア人の弟子たちを取り囲み軍用トラックに押し込めたのだ。平和行進の人々もバスでイングーシまで戻された。平和行進は潰された。
とはいえ、モスクワに強制送還されても寺沢さんは諦めなかった。翌月、再びナザランからの平和行進を開始するのだ。だが直後、自分たちを歓待してくれたサマシキの人々が虐殺されたのを知る。
「ショックでした。国境まで行くと、サマシキからの避難民が泣いて歩いているんです。ロシア軍は地下室に隠れていた住民に手榴弾を投げ、男たちを銃殺し、母親の前で赤ん坊を戦車でひき殺し、最後は火炎放射器で住民を家ごと焼き払ったという話でした。八千人の町で三百人以上が殺されたんです!」
あまりもの残虐行為に憤りの炎を燃やすと同時に、寺沢さんは改めて誓った。何が何でもチェチェンを歩き通すと。
非暴力の力
九五年七月、グロズヌイでロシアとチェチェンの和平交渉が始まる。そのとき、ある町で一家七人が惨殺され、ロシアの仕業だと血気に逸る民衆が、抗議のため遺体を交渉会場まで運ぼうとしていた。それを妨害するロシア軍と一触即発の状況になった時、寺沢さんは先頭を歩くよう依頼された。寺沢さんは、みんなに非暴力を約束させてから歩き始めた。弟子たちがウチワ太鼓を撃つ。日本山妙法寺の紫の旗が翻る。みるみる群衆が集まってきた。
平和行進はロシア軍のバリケードも突破し、大統領官邸前広場に到達した時には、広場は五万人の「チェチェンに自由を! 独立を!」の声で凄まじい熱気に溢れていた。
翌日はそれ以上の大行進になり、太鼓の音と群集の数に検問所のロシア兵が逃げ出した。「非暴力運動が平和を導く確かな力になることを実感しましたね」
それは同時に、平和行進がロシアの脅威にもなっていたことを意味する。数日後、寺沢さんと弟子の八人は突然逮捕された。
目が潰れるくらいにきつい目隠しをされ、頭から袋をかぶせられ、手かせをされ、強制収用所に連行される。壁に頭をぶつけられ殴られ、冷たい床に這いつくばらされ、少しでも動くと腹を蹴られた。寺沢さんはここで死を静かに覚悟したという。
「みんなで一心にお題目を唱えたり、太鼓を撃ったりで心は落ち着いていました」
幸い、大きく報道されたためか、寺沢さんたちは一週間後に釈放された。だがチェチェンでは、収用所に連行されたまま一五〇〇人が未だに行方不明だ。一〇〇万人の人口のうち一五万人が戦死。三五万人が難民化。三〇〇ある村のうち二五〇が壊滅した。それくらい凄まじい状況下での平和行進だったのだ。
九六年八月、停戦が実現したが、九九年八月、モスクワで頻発する爆弾テロのチェチェン人テロリストを撲滅するという根拠のない口実で、第二次チェチェン戦争が勃発した。 そして、寺沢さんは、二〇〇〇年四月のジュネーブでの国連人権委員会でロシア軍の蛮行を非難したことから、六月にロシアからのビザ発給を停止されてしまう。だが、本人に諦める様子は一切ない。
「いやあ、名誉のブラックリストですよ! チェチェンに行けなくても、私の使命はまだまだあるんです。コソボ空爆はあれだけ報道されたのに、チェチェンで進行しているそれ以上の戦争犯罪をメディアは伝えず、国際機関も裁かず、どの国もただの一ドルの支援もチェチェンにしていません。私はこれを訴え続けていきます」
寺沢さんは年に数度来日しては、外務省に、チェチェン戦争を後押しするロシアへの経済援助の凍結を訴える。
また、黄色い袈裟姿で世界のどこにも現れる。フランスの国会ではチェチェン戦争批判の記者会見に出席、国連人権委員会への参加、国連本部へのアポなし訪問(!)、バチカン法庁での話し合い・・。チェチェン以外のことでも、昨年に限れば、インドとパキスタンの核実験を諌めるため、弟子一〇人と両国を三ヵ月をかけて平和行進をした。イスラエルでも装甲車の轟音のなかで平和行進。そして、今年の三月はバグダッドに赴き、国連前で断食座り込みと一四〇キロの平和行進を計画した。
その運動の特異性から距離を保つ人もいるかもしれないが、私は、寺沢さんの姿に真の平和運動を感じるのだ。今回のイラク空爆もそうだが、戦争勃発に合わせて「戦争反対」を叫ぶのではなく、寺沢さんは日々平和を考え、そこにどんな権力が待ち受けていようと、ただ歩き続けているからだ。
寺沢さんは、日本山妙法寺の僧侶ではあるが、その組織力に頼らずに一人で行動し、広大な平和ネットワークを形成してきた。日本山妙法寺のある僧侶はこう語った。
「『和合』という言葉がありますが、私どもの運動は、全体が動きやすいようにするには、全体で理解して、全体の一部として動く必要があるのも事実です。寺沢上人ほどの実力ある方は、一人で動くのではなく、こちらへもと誘いたい気持ちもありますが、こればかりは時期の問題です。今、寺沢上人は自分なりの修行をしているのだと思います」
なぜ歩き続けるのか? これに対する答えは非常に明快である。
「困難を求めることこそ、日蓮の弟子として、法を求める者の姿勢だと思います。お師匠様の教えでもあるんですが、私は、仏弟子としての修行は『歩く』こと以外にないと思っています。そして、非暴力で歩くことだけで、励まされる人々は多いのです」
次はどこの国を歩くのだろう?
「これからも、因縁さえあればウチワ太鼓だけでどこの国にも行きますよ。私は地球を遊行する一旅僧として生きていきます」
未だに回答はない。だが歩く。
極寒の地も酷暑の砂漠も、雨の日も砂埃のなかでも寺沢さんは歩いて行く。歩き続けるその姿にただ合掌したい。
| 緊急メッセージ 2006年1月9日、寺沢上人は、チェチェン問題を知ってもらうためにハンストを続け瀕死の状態にあるイブラギモフさん支援のための声明を各国語で発表した。 「この人を見よ」 サイード・アミン・イブラギモフ氏無期限断食に寄する緊急メッセージ 日本山妙法寺 寺沢潤世 二〇〇六年一月九日 ウクライナにて 南無妙法蓮華経 救国、救世のまことの勇者、慈悲の人には、軍隊も戦略も、大量殺人兵器も、自爆テロも必要ではない。無私にして真実たらんとしつづける人は、ただ一人で全世界に立ち向かい、そして世界に勝つことができる。 長年にわたって私の知るサイドアミン・イブラギモフは、彼の母国と同胞を、暴力的な滅亡と絶滅から救わんがため、熱情的な非暴力闘争をしつづける。このような真に勇敢な二十一世紀の英雄的サッチャグラヒ(真実のための戦士)である。 今も続いているチェチェンでのジェノサイドは、ポスト冷戦期、二十一世紀の終末的な受難劇である。全世界が真実を裏切り、真実をいけにえにした、冷戦後の「ニューグレート・ゲーム」は、このいけにえの上に今も演じられつづけている。だれも逃れることはできない。傍観者はいないのだ。誰も、が白昼堂々とチェチェンの国をはりつけにする刑に参加しつづけている。 私の古い精神的同行者、サイドアミン・イブラギモフは、今、静かに彼が選んだ最後の運命に従おうとしている。しかし、どんな雄弁やマススローガンにもまして、彼は世界政治の本当の顔をあばきだして見せた。 彼の自己犠牲は決して虚しく終わらない。彼の例につづくことによって現代世界はその狂気と自己欺瞞から立ち直るのである。 ロシアは力によってチェチェンを征服することは決してできない。チェチェンの魂を破壊することもできない。 ロシアは世界を欺きつづけることもできない。ロシアはとうの昔に真実を失っている。サイドアミン・イブラギモフは真実と自由の不滅のチェチェン精神を、すでに実証してみせた。 以上 英語: http://chechennews.org/dl/20060109_apeal-eng_on_Said-Emin.pdf ロシア語: http://chechennews.org/dl/20060109_apeal-rus_on_Said-Emin.doc 今回の断食では、最悪の事態も考えられるので、寺沢上人とチェチェン人のお弟子はどうしても駆けつけたいとのことです。また、イブラギモフ氏周辺のチェチェン人たちも、宗教者である寺沢上人の到着を心待ちにしています。この支援金は、その行動費にあてられます。金額が必要額に満たなくても、数日中に送金します。どうぞ主旨をご理解の上、ご協力をお願いします。 送金先: 郵便振替口座番号:00180−6−261048 口座名称:チェチェン連絡会議 ※通信欄に「寺沢上人支援」とお書き添えください。 |