
�Y�p�ɒ��ޏZ��n
�T���v���C�{�[�C07�N8��13�����ɉ��M
| ���疜�~���������䂪�Ƃ�������ˑR�X���n�߂�B�͂��܂��ُL�ɏP����B�����A���Ȃ��̎���̒n���ɎY�p�����߂��Ă�����A�����͂����Ȃ邩������Ȃ��B���ہA����Ȉ����ɏP���Ă���c�n����ނ����B |
�P�D�������u�c�n�i���R�����R�s�j
 |
| ����̒�����@��ƁA�����ɏL�������y�����ꂽ |
�@��N10���A���R�s�́u�������u�c�n�v�i34��120�l�j�ɏZ�ފ��q�K����́A�ˑR�A�����œ|�ꂽ�B�������̂͋ߏ��̓����N���B
�u�ق�̐����O�ɉ�����l���|��Ă�����ł��B���v���Ɛ���������A�w���`�A���`�x�Ƒ����̈ӎ������������x�ŁA�~�}�Ԃł͂悾�ꂪ�_���_���ł����v�i��������j
�@�f�f���́u�����_�K�X���Łv�B����ȃK�X���Ȃ����ɗN�����̂��B���͐��\�N�O�ɖ��߂�ꂽ�Y�Ɣp�����ɂ���B
�@�c�n�Z�������̑��݂�m�����̂�3�N�O��7���B�����H���ŋƎ҂����H���@��Ԃ��ƁA��ʂ̍����y�ƍ��������o�Ă����̂��B�s�ƁA�c�n���������u�����o�X�s���Y�J���p�j�[�v�i���u�����z�[���f�B���O�X�v�B���R�s�j�̒����ŁA�n����������l��27�{�̃g���N�����G�`�����i���܁j��26�{�̃x���[���Ȃǂɉ�������Ă������Ƃ����������B
�@�����āA��삳�������߂ĕ����������Ƃ�����B����́A���̓y�n�ł́A�P�X�U�V�N����u�������H�Ɓv�Ƃ�����������Ă�����Ђ��A�p����y���ɐ��ꗬ���Ă������Ƃ��B
�u����ō��_�������܂����B93�N�̓����ȍ~�A�ȂƖ��̓A�g�s�[�Ɩ������ɁA���q�Ɩl�͖����@���ɔY�܂���A�Z�������l��������ł��v�i��삳��j
�@���ہA04�N�X���A�s�����{�������N���k�ł��A65�l�̑��k�҂̂���42�l�ɔ畆����@���Ȃǂ��m�F����Ă���B
�@
�@���N�V����{�A���̒c�n��������B�c�n�ɂ͊Â����邢�s���L���Y���Ă���B�u����A������v�ƁA�������A�����������̒����ŊJ�����{�[�����O���̊W��n�ʂ���O�����B�@���߂Â���ƁA�H�Ɩ��ƃS�}�����������ĕ������悤�ȓ����ɓf���C���N�����B
�@���������ł͂Ȃ��B�c�n�̂��������̕���ǂɂ͋T����A�n�ʂ��E��ł���ꏊ������B
�u�n�Ւ����ł��B�ق�A���̋T��́A�ꎞ�́A�J�j�̖A�̂悤�Ƀu�N�u�N�ƃK�X���o�Ă܂����v�i��삳��j
�@�����ւ�ȏꏊ���B�����A���������A�Ȃ��Y�p�̏�ɒc�n������̂��H
�@�����������ƒ�~�����̂́A82�N�A�����Ƃ̓y�n�����_�������Ă��炾�B
�@����ȑO�A����������͑ς����Ȃ����L�����Ӓn��ɗ���Ă��āA�ߗZ�������͊��x�ƍs���ɉ��P��i���A���ہA���R�s�⌧��10��ȏ���w�����s���Ă����B���������A�Y�p�����Ђ̓y�n�ɓ������邱�Ƃ��K������@���͂Ȃ��������߁A������i�͍u�����Ȃ������B
�@�Ƃ�����A���̓y�n�𗼔�����肷��B
�@�������A�������ꂽ�y�n�ł���̂ŁA�����ƈ������͂��̓y�n�̏��n���ٔ����ɂ������B���̌��ʁA���������P�ނɂ�����A�u�����t�������������āi�����ɓy�n���j�����n���v���Ƃ�����a�������킳���̂ł���B
�@���̌�A�Y�p���P�����ꂽ�����m�F���鉪�R������S�[�T�C�����o���̂ŁA�����́u�i���łɁj�y�뉘���̔F���͂Ȃ������v�Ƃ������ƂŁA�Y�p�̏�ɒc�n�����Ă��A87�N�̕����Ȍ�A������ɓy�n�̌o�܂�������Ȃ������B
�@
 |
 |
 |
 |
| �����������p�ɊJ�������B�җ�ɏL���B | �c�n�e�̐�ɂ͓�̍����������o���Ă��� | ��̍����ɂ���̂��������u�c�n | ����Ƃ̒�ɊJ����ꂽ�����p�̌��B����������A�K�X�����N���Ă��� |
�@�����āA04�N�ɓy�����獕���y�ƍ��������m�F���ꂽ�B
�@�ˑR�����o�����������ւ̕s���ɁA������04�N10���A�T����c�����鎄�݂́u�����ψ���v��ݒu�����B����ʼn����y�낪��������邩�Ǝv������u�Ƃ�ł��Ȃ������v�Ɗ�삳��͐U��Ԃ�B
�u�ψ���7�l�S�������R��w�̋����ŏZ���̓[���B�R�c�͔���J�A�c���^�{�����s�B�ψ����̐�t���O���w���i�����j�͌���ɗ����A������3��̐R�c�ŁA05�N1���ɂ�����2�y�[�W�̈ӌ������o���ďI���ł��B�w�ُL�ɂ��s�����͂��邪�A���N�ւ̉e���͒����Ɍ��O����Ȃ��x�ł����āv�i��삳��j
�@�s���Ȃ̂́A�s���ł��鉪�R�s�����̌��_�������ɁA�Z���ւ̋~�ύ���Ȃ��u���Ă��Ȃ����Ƃ��B���R�������R�s���A�����ɊJ�������o���������҂ł��邩�疳�W�Ƃ͂����Ȃ��B
�u�܂������̑S�e��m�肽���B����ɂ��e�˂ւ̋~�ύ����ł��܂��B�ł��y�뒲�������x�˗����Ă��A�s�͓����܂���v�i��������j
 |
| ���镻�ł͎肪����قǂ̋T�������B���̕�C�̌� |
�@�����ŁA�s���ۑS�ۂɐq�˂Ă݂��B
�\�\�y�뒲���͍s��Ȃ��̂ł����H
�u�l���Ă���܂���B���̓y�n�̎��Ӓn��ɂ����ː�������A�������g�債�Ă��邩���Ȃ����킩��܂�����v
�\�\�����Ȃ闝�R�ł��Ȃ��̂ł����H
�u�����Ȃ闝�R�ƌ����Ă��E�E�B���̕K�v���Ȃ�����ł��v
�@���̉ɋ~�ςւ̈ӎu�͂Ȃ��B�����āA�s�����ł͂Ȃ��B��삳��Ɠ�������́A�u�Ў�Ԃł͉����ł���v�ƁA��蔭�o��ɑސE���Z���g�D�u�������u�c�n�~�ϋ��c��v�������B���ȁA�@���ȁA���x�A���m���A�s���ȂǂɊ����̎�����v�]�����o���Ă����B�����A�̑����́u�s�Ƒ��k���v�Ƃ������̂���B����ɂ́A���c���s�c���^��}��킸���S�B
�@����ȂȂ��Ŋ�삳��͓|�ꂽ�B����́A���������ƌ@��Ƃǂ������y������A�Ƃ̒����ُL�������A���X�K�X�x��@����i�I�j�B
�u����̏a�J�ł̉����A����A�q�g�S�g����Ȃ��ł���v�i��삳��j
�@�����Ă�����s���Ȃ̂́A���{�l�Ȃ瑽���̐l���m���Ă����̃e���r�ԑg�������Ɏ�ނɗ��Ă��Ȃ���A���̕��f���O�ɂȂ��ē˔@���f���~�����߂����Ƃ��B�����������̗͂������Ă���̂��H�@�s�����c��������Ȃ��B�}�X�R�~������傫�ȗ͂Ő��䂳��Ă���B�����������̂́A���̂܂܂ł́A�������u�̐l�����̂��Ƃ�N����莋�����ɁA�������čD�]���邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@�����Łu�`���Ȃ���I�v�@�ƁA�@�c�n�̉����̈�[�����ł��m�낤�ƁA�Z���L�u�͂������o�������A���N�A����̓y�댟���Ԓ�����ЂɈ˗������B���̌��ʁA���o����Ă͂����Ȃ��V�A���������i�_�J���j�A����l�ȏ�̉��A��f�A�x���[�������o���ꂽ�̂��B��͂�c�n�S��̒����͋}���ł���B
�@�������u�ł̂�����̖��́A���疜�~�������Ƃ����̈�Y�ɂȂ������Ƃł���B��������́A��s�Ɏ���S�ۂł̗Z�����k�ɍs�������Ƃ�����B����ƁA�u�������u�̕����͒S�ۂɂł��Ȃ��v�ƗZ����f��ꂽ�B�Ƃ̎��Y���l���[���ɂȂ����Ƃ������Ƃ��c�B
�@��삳���́A�������̐����ӔC��ӂ����Ƃ��āA������ǂ閯���ٔ����l���Ă���B�V�����y�n�ŐV�����ƂɏZ�߂邾���̕⏞�����߂�̂��B
�u���S���ďZ�݂����B���ꂾ���ł��v
�Q�D���ԑ�j���[�^�E���i���m�����q�s�j
 |
| �ˑR�����z����2���̉ƁB���͐l������Ȃ����A�����̒n�Ւ������i�� |
�u����A�������O�����T�L�����Ă邼�I�v
�@�u���ԑ�j���[�^�E���v�̏Z���A�ێR����̐��̕�������ƁA�H�ʂƉ��̊Ԃɒi���ƌ��Ԃ��ł��Ă���B���m�����q�s�̓��ԑ�j���[�^�E���̈�p�͍��������ƒ���ł���B
�@20�N�O�A���ԑ�ւ̓����͑A�]�̓I�������B�����A�����������A�t�q�i�Ɨ��s���@�l�E�s�s�Đ��@�\�j�������������D�Ǖ����B�؉��p�q�����88�N�A��R5���ځi107�ˁj�ɓ��������B�����āA���N��Ɉٕς��N�����B
�u93�N������h�A���J���Ȃ��Ȃ�����ł��B���̂��тɃh�A�̉������܂����B�ł��A���C�̂������ȂƁc�v
�@97�N����A�T���ڏZ���́u���������v�Ɗ����n�߂��B�Ƃ��X�����A��ł́A���炽�Ȃ��Ȃ������炾�B
�����̔��o��06�N1���B04�N��05�N�A�ד��m��2���̉Ƃ��������œ]���������ƂɁA�t�q�͏Z����������Â��A�n�Ւ����ƒn���ɂ���u���R�E�ɂ͑��݂��Ȃ������v�̑��݂�F�߂��̂��B�����͍ő��X�a���������̂ŁA�t�q��������������̂������B
�@�����āA2���̉Ƃ̉�̐Ղłt�q���{�[�����O����������ƁA���ɒn��4�b����8�b�ɂ킽��A�^���������܂݂�̓y���͐ς��Ă����B�ێR�����̃T���v�����r���l�ߕۑ����Ă���B�^�C���̕������悤�ȓ����ł���B
�@�����Ȍ�A�����t�q���Z���~�ςɓ������Ƃ��Ȃ��B�ێR�����06�N4���ɁA��������ڎw���Ă̏Z���g�D�u�l�����v�����������B���R������B
�u�����t�q���R���R���咣��ς��ĐӔC����ɏI�n����B�����������Ȃ��v
���̒n�ł́A�u���t�H�Ɓv�Ƃ�����Ђ����q�����̎Y�p���̂ĂĂ����B���̎���������Ȃ���A�t�q�͓����́u���R�E�ɂ͑��݂��Ȃ������v���̂��Ɂu�����w�̖��v�ƒ������A���́u�������Ɏ�菜���Ȃ������Y�p�v�Ƃ̐������u�����y�͔S�y�v�Ƃ̕\���ɕς����B
 |
 |
 |
 |
| �n�ʂɋT�����Ă��� | ������𐅕��ɂ����猄�Ԃ� | ���̎Y�p�����́u�S�y�v�Ɛ������� | �j���[�^�E���q��ʐ^�B�Ԃ��g�����t�H�Ƃ̑��ƒn |
�@���ہA���͍�N10���A�y�뒲���̌��ʂ����\����̂����A���̌��ʂ͗\�z�ʂ�u���������L�Q�����͌�����Ȃ��v�Ƃ������̂������B
�@����A�u�l�����v�ł́A�Ǝ��ɍ̎悵���y��T���v���Ԍ����@�ւɑ������B����Ɓu100���Y�p�Ǝv���ĊԈႢ�Ȃ��v�Ƃ̌��_��̂ł���B
�@���߂Č��ɐq�˂��B����͎Y�p�Ȃ̂��ƁB�́A�u�Y�p���Ⴀ��܂���v�B
�\�\�Ȃ��ł��傤���H
�u�Y�p�Ɣ��f����ޗ����Ȃ��ł��v
�@�}�j���A���̋ɂ݂��c�B
�@����ɏZ�������ꂽ�̂́A���Ƃt�q���A�u�Y�p�������Ȃ����������v�u�y�n���������Ȃ��t�q�������v�Ɣᔻ�������A��N8���ɂt�q���A�n�Ւ�����ɂ���������p�𐿋����邽�߁A�����i�������Ƃ��B
�u�Z���̋~�ς͂������̂��ł��B�����V�l�{�݂ɓ��낤�Ǝv���Ă���l�ł��A�Ƃ�����Ȃ��̂ŁA�����v������Ă���̂Ɂv�i�؉�����j
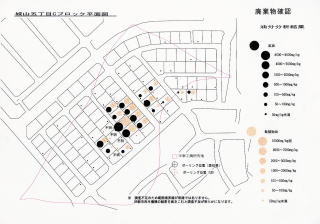 |
| �t�q�̎�������ɁA�ێR���쐬�����j���[�^�E���̉����}�B�����͈͂͂܂��L���͂��ƊێR����͐������� |
�@�t�q�́u�Y�p�����̐ӔC�͌��������ׂ��B�������A�n�Ւ����ւ̑Ώ��ɂ͂ł��邾���̂��Ƃ͂��܂��v�Ǝ咣����B���ہA��N�A�n�Ւ����̏Z����W���b�L�A�b�v���Ă̏C���Ă��Z���ɒ����B�����A�u�Y�p�̑S�ʓP���v���肤�Z���͂�������ۂ����B
�@���������A��R5���ڂɂ́i2�����ړ]�����̂Łj105�˂�����̂ɁA�t�q�͒����͈͂ƎY�p�͈͂��i�܂�~�ϔ͈͂��j�Ȃ���31�˂ɐ������������߁A�Ƃ��Ă��ۂݍ��߂Ȃ��Ă������B
�u���t�̕~�n��31�˂̕~�n���L���B�����ɁA�������͈̔͊O�̑�n�ŁA�@�킵���y�𐅒��ɐZ������A�����������܂����B�l�������]�ނ̂́A�p��������������Ȃ�A�V�����y�n�ł̐V����p�ӂ���Ȃ�́A���S���ĕ�点��ۏł��B���̂��߂ɂ́A�܂��S��I�ȓy�뒲����]�݂܂��v
�@�ێR�����́A������t�q��s���Ƃ̌��𑱂��Ă����B
�@���āA�s�K�ɂ��Y�p�̏�Ɍ��Ă�ꂽ�Z��͂܂�����B
�@���{���s�ɂ��镶��c�n�́A87�N������Ƃ��X���n�߂��B�S�~�A�ޖA�u���b�N�A�v���X�`�b�N�Ȃǂ̎Y�p���g�������n�Ղ̏�Ɍ��Ă�ꂽ�̂��B
�@�R�����̖^�j���[�^�E���ł��A�R�ł̑����̈ꕔ�ɎY�p���g���A10�ˈȏオ�n�Ւ��������B
���l�s�s�n��̖^�V�z�}���V�����́A���̕~�n���H��Ւn�ʼn�������Ă������ߕ\�y�͓���ւ������A���͏��߂���A�s���n�Ւ�����̏d�_�n����ɂ�ł���ꏊ���B�����\��҂́u�܂��Y�p�����܂��Ă邩���B�_��������悤���v�Ɩ����Ă���B
�@��������ȏZ��ɂ��������ꍇ�A���{���w���̔����N���́A���{�����͎��̓�����Ȃ��ƌ��B
�u�ꎞ�I�Ɉ����z���ԂɁA�����̂�Ǝ҂��Ƃ̉�̂Ɣp�����̏����A�y��̓���ւ��A�Ɖ��̐V�z�����A�����ɍē������邱�ƁB�܂��́A�V�����y�n�ł̐V�z�Z��̈������邱�Ƃł��v
�@�������A����́A�����Ǝғ�����p���S���Ă��ꂽ��̘b�ł���B�����āA����Ȃ̂́A���������y�n�ɓ�����Ȃ����Ƃɐs����B�������c�B
�@�������≤�t�H�Ƃ̂悤�Ɏ��Ђ̓y�n�ɔp�����𓊓�����s�ׂ́A�����́A�p�����ւ̖@�K�����Ȃ������̂ň�@�ł͂Ȃ������B����ȍH��͓��{�e�n�ɂ������̂ŁA���̌��ʁA�Y�p�Ȃǂœy�뉘�����ꂽ����͍��A�S����30�������ȏ�i�I�j����B
�@�����Č��݂̖@�̌n�̌��ׂƌ�����̂��A���Ƃ��u�y�뉘�����@�v�i03�N2���{�s�j�Ȃ�A���̓y�낪��������Ă��邩�ǂ����ׂ�`���́u���݂̓y�n���L�ҁv�ɂ��邱�Ƃ��B�������ꂽ���Ƃ�m�炸�ɓy�n���w��������l�ɂƂ��āA����͂����B
�@�܂����Ƃ��A�u�i�m�@�v�i2000�N4���{�s�j�Ȃ�A�H���X�E�Z��[�J�[�E�����Z���ЂȂǂ̏Z����҂��A�V�z�Z��Ɍ��ׂ��Ȃ����Ƃ�10�N�ԕۏ���`�����̂����i���\�N���Z�މƂɂ�����10�N�̕ۏƂ����̂��������Șb���j�A���̖@���͓y��̌��ׂɂ��Ă܂ł̓J�o�[���Ȃ��B
�@�܂�A�ǂ���̖@�����A�y��Ɍ��ׂ������Ă��A�N���ʓ|�����Ă���Ȃ����x�ɂȂ��Ă���E�E�B
�@�Ō�ɁA���S���ďZ�߂�y�n�I�т̃|�C���g���Љ�悤�B�哈�����z�v�������i���s�j�̑哈�����͂���ȃA�h�o�C�X������B
�u�y�n�w���̍ہA����y�͗v���ӂł��B���ߓy�̈���͂T�`10�N������̂ŁA������y�������A�Y�p�������Ă��Ȃ������ߏ��̐l�ɕ����܂��傤�B�}���قŌÒn�}�ׂ܂��傤�B�@���Ȃœo�L�������Βn�����킩��܂��v
�@�n���̎Y�p���ɂ݁A�n�Ւ������N�����Z��n�͍��������邱�Ƃ��낤�B���߂āA���ꂩ��Ƃ��l�́A�T�d�ɓy�n��I��ł��炢�����B